「盆栽」は大中小といったサイズ、樹や草に大別される種類、そして樹の形といった具合に分類されています。
This post is also available in: CN (CN) TW (TW) EN (EN)
大きさの分類
手のひらに載るものから1メートルを超えるものまで、盆栽には様々な大きさがあります。それぞれに魅力はありますが、扱いやすいのは1人で持ち運びができるくらいのサイズ。マンションのベランダで育てるにもおすすめです。

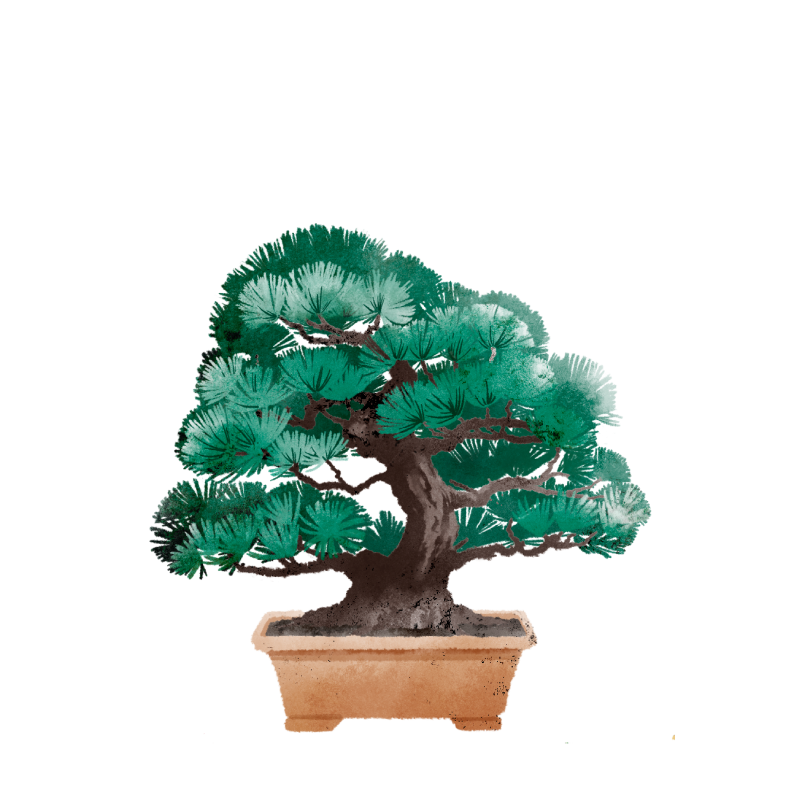
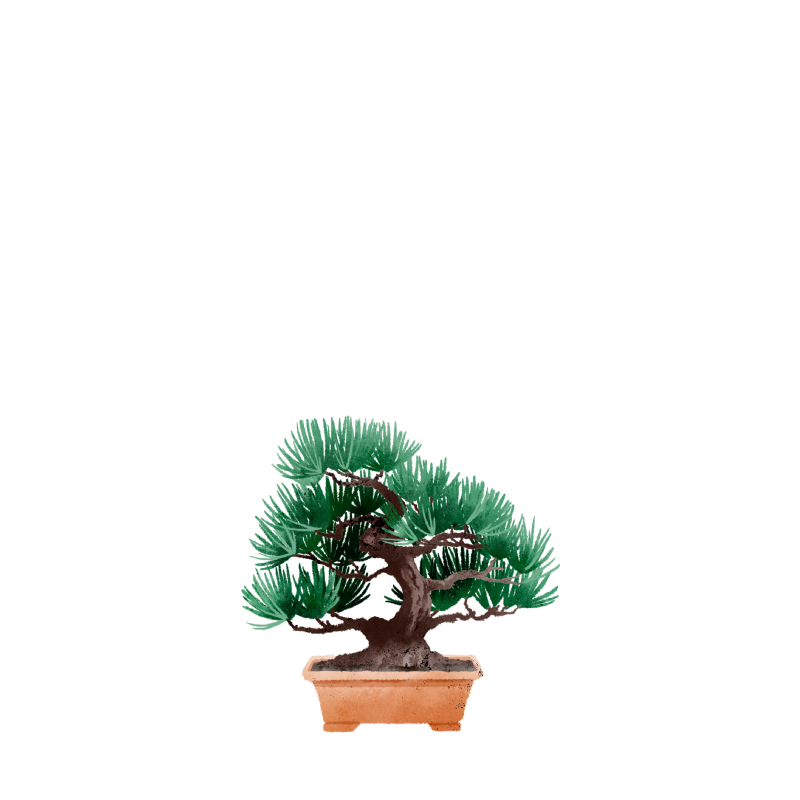
10cm以下はミニ盆栽ともいう。

10cm以下はミニ盆栽ともいう。
盆栽の種類
主な見どころを中心に5種類に分類
盆栽は大別すれば「樹」と「草」に分けられ、「樹」は主な見どころによって「松柏」「葉もの」「花もの」「実もの」の4種に分類されます。このうち「松柏」以外は総称して「雑木」とも呼ばれます。
季節ごとにさまざまな表情を見せる盆栽は、種類によってそれぞれ観賞期が異なります。
花を楽しむ「花もの」は主に早春から初夏にかけてが観賞期となり、「実もの」は果実が色濃く熟す秋から初冬にかけてが見頃となります。葉姿を楽しむ「葉もの」は、新緑も秋の紅葉も美しく、さらに落葉後の寒樹の姿も大きな見どころです。
冬も緑の葉を保つ「松柏」は一年中観賞できますが、その年の葉がきれいに揃う秋から冬にかけてがもっとも美しい時期といえます。
以下、それぞれの特徴と楽しみ方を紹介します。
松柏(しょうはく)
盆栽といえば、多くの人が思い浮かべるのが松類ではないでしょうか。
松類に代表される常緑針葉樹は一年中緑を楽しめます。数百年もの樹齢を重ねた名品名木も多く、盆栽の飾りでは松柏を主木にするのが昔から王道とされています。
力強く優美さも兼ね備えた松柏は、風格、古色をたたえたあらゆる樹形に仕立てることができます。なかでも特に人気のある黒松、五葉松、真柏は松柏の御三家とも称されます。


花もの
花が開いたときが最高の観賞期となる樹種を「花もの」といい、鮮やかな色彩や香りが明るく華やいだ雰囲気を醸し出します。
花ものの多くが早春から初夏にかけて開花。寒のうちから咲く梅を嚆こうし矢として、ツバキ、桜、ボケ、バラ、サツキ、アジサイなどが代表的な花もの樹種となります。
見どころはもちろん花ですが、盆栽であるからにはやはり、幹枝の模様に趣きがあることや樹形が整っていることも必要です。


実もの
実が熟した姿を観賞する樹種を「実もの」といいます。実をつけた様は豊かな稔りの象徴といえ、落葉後の枝に残った実は季節の移ろい感じさせます。ほとんどの実ものが秋から初冬にかけて実をつけますが、グミ類など春や夏に結実するものもあります。
秋の山里の風景を思い起こさせる老鴉柿などの柿類、食用のミニチュア版のような可愛くリアルな実のリンゴ類、小さな赤実をたくさんつけるウメモドキやカマツカ、ピラカンサ、他には見られない紫色の実が美しいムラサキシキブなどが代表的な実もの樹種。実を引き立たせる色合いの鉢に入れると、実ものはより魅力が増します。


葉もの
季節ごとに変わりゆく葉の表情を主に楽しむ盆栽を「葉もの」といい、一般的には冬に落葉する広葉樹がそれにあたります。
春の芽吹き、初夏の新緑、秋の紅葉、そして落葉後の裸木となった「寒樹」の姿と、四季の移ろいをもっとも楽しめる盆栽といえるでしょう。多くは冬期に落葉しますが、チリメンカズラなど常緑の葉ものもあります。
概して丈夫で育てやすい樹種が多く、ビギナーにもおすすめといえます。モミジ、カエデ、ケヤキ、ブナ、シデ類、ヒメシャラ、イチョウなどが代表的な葉もの樹種となります。

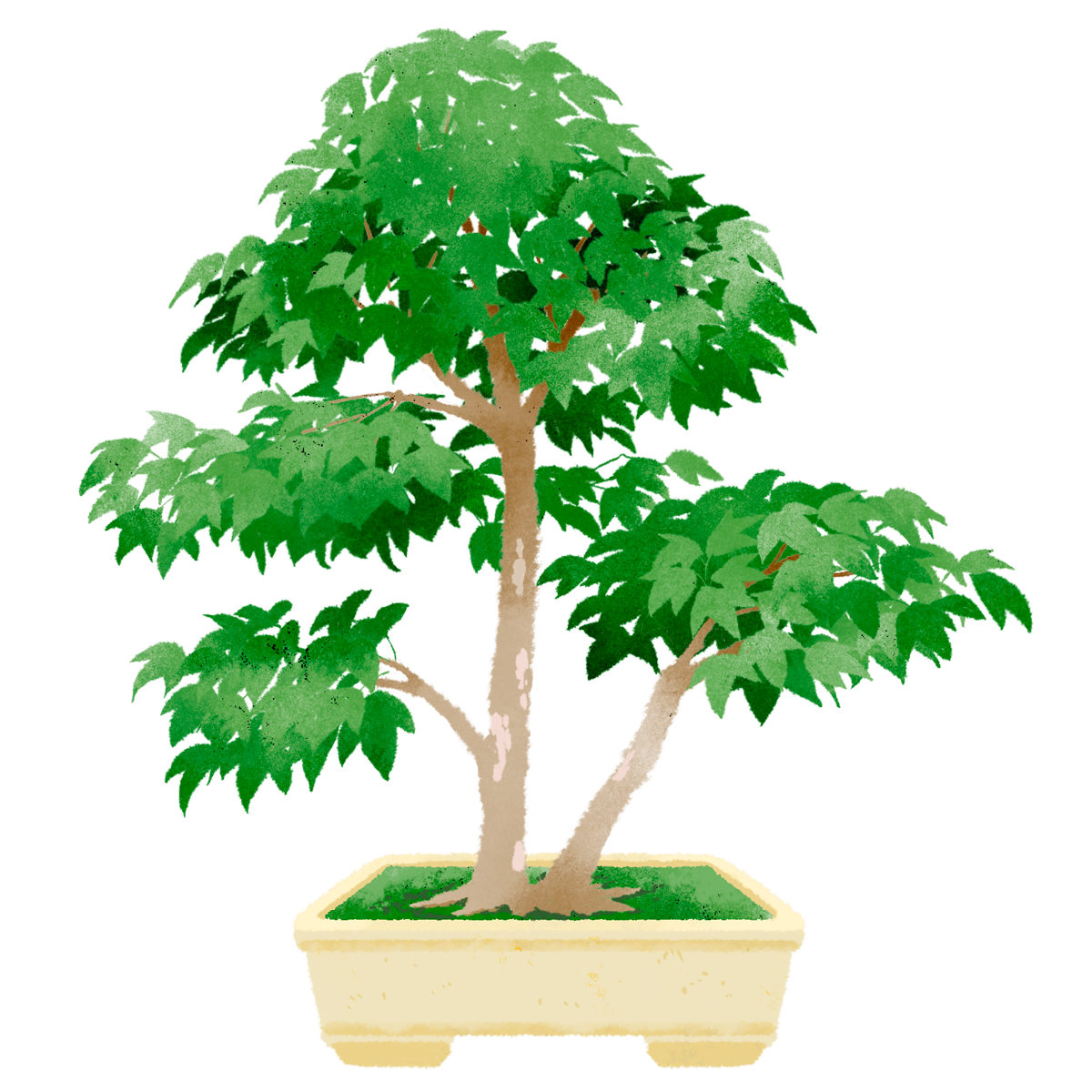
樹形

直幹(ちょっかん)
幹がまっすぐ真上に立ち上がり、根は四方八方に張り、樹姿は樹冠を頂点とした不等辺三角形を描くのが理想とされます。自然樹の大木を忠実に再現した樹形といえますが、幹をまっすぐに伸ばし、同時にコケ順もよくするのは高度な技術を要します。

模様木(もようぎ)
幹が前後左右に曲がりながら上へと伸びる樹形で、直幹の幹に緩やかなSの字を描く曲(模様)がついた姿と考えればよいでしょう。盆栽ではもっともよく見る代表的な樹形といえ、幹の曲線美を楽しみます。

吹き流し
高山や海辺で強風にさらされ、幹から枝先まで一方向になびいた姿を表現した樹形です。松柏類や枝がよくほぐれた葉ものがこの樹形には似合います。
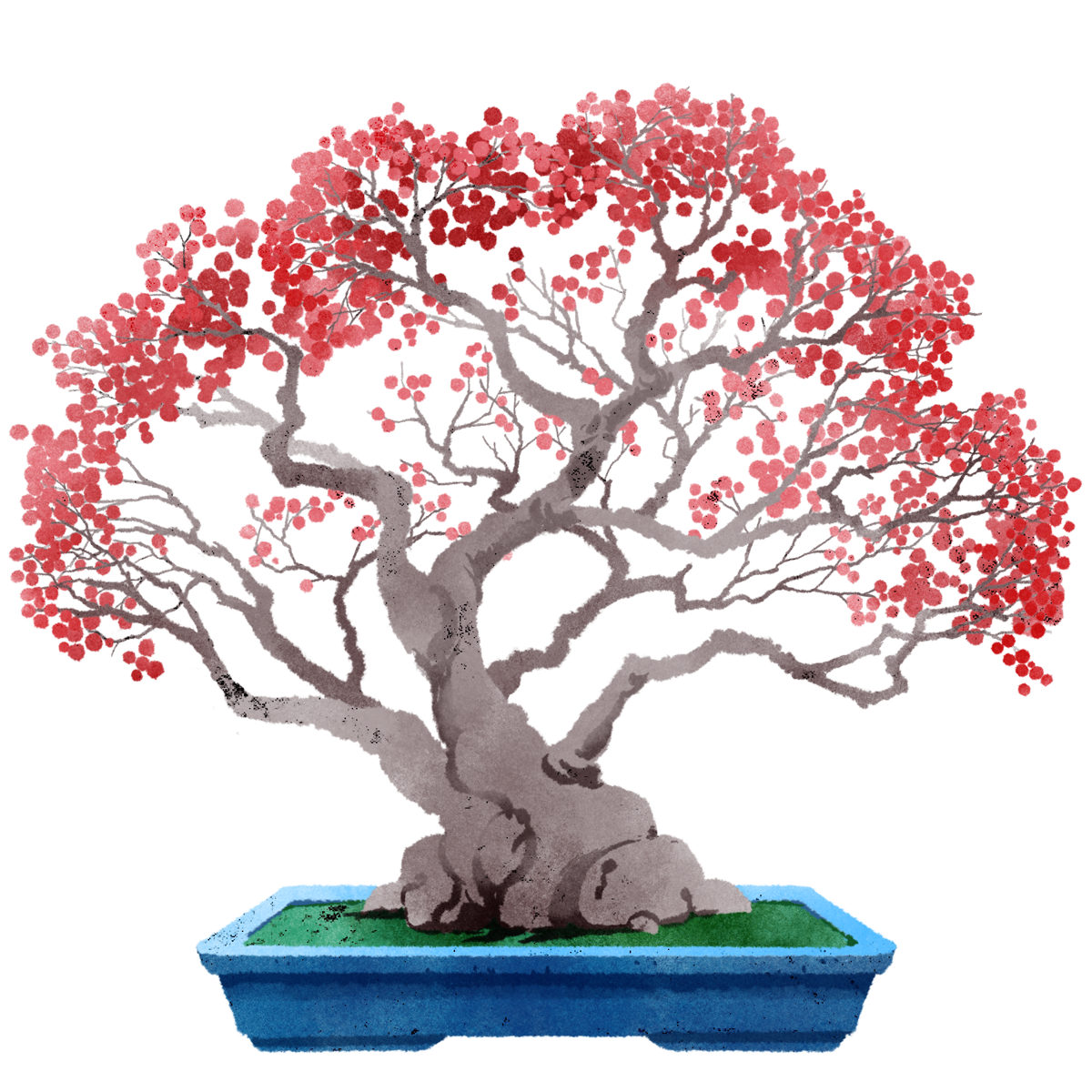
株立ち
1つの株の根元から複数の幹が立ち上がった樹形で、幹の数は3幹・5幹・7幹など奇数が基本となります。主幹と他の幹との調和や全体のまとまりが見どころです。

文人木(ぶんじんぎ)
細い幹がすらりと伸び、幹の下方には枝がなく、全体に繊細な立ち姿の樹形です。明治期、軽妙洒脱さを良しとした文化人がこのような姿の盆栽を好んだことから、この名が付けられました。

寄せ植え
同樹種の株を複数、1つの鉢に植え込んで森や林の景を表した樹形。盆栽では1樹種で作るのが普通ですが、山野草では複数の樹種や草ものを用いた寄せ植えもあります。

懸崖(けんがい)
断崖絶壁に根を張ってたくましく生き抜く力強い姿を表現した樹形です。幹や枝の下端が鉢底より下に来るものを懸崖、鉢底より下がらないものを半懸崖と呼び分けます。
![]()



